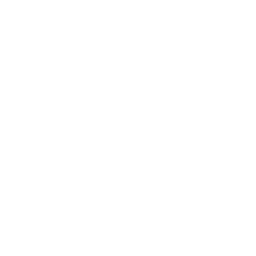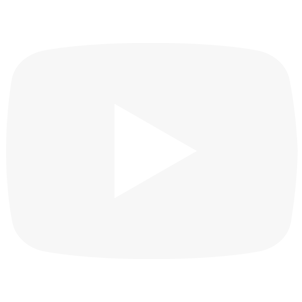Education
所沢店
scrollable
写真人文学:アウラの消失についての考察
投稿日:2017/5/20
9280 0

写真人文学という教材を基軸として、ライフスタジオの写真というものを考えていきたいと思います。
今回は写真人文学 第1章 『ベンヤミンのアウラ』からです。
また写真人文学の内容に関しては、Mr.LEEのブログを是非ご参考くださいませ。
―”To perceive the aura of an object we look at,
mean to invest it with the ability to look at us in return.”―
Walter Benjamin
「私たちが見ている被写体のアウラを認識することは、
私たち自身を見つめようとすることの代替行為となる。」
今回は写真人文学 第1章 『ベンヤミンのアウラ』からです。
また写真人文学の内容に関しては、Mr.LEEのブログを是非ご参考くださいませ。
―”To perceive the aura of an object we look at,
mean to invest it with the ability to look at us in return.”―
Walter Benjamin
「私たちが見ている被写体のアウラを認識することは、
私たち自身を見つめようとすることの代替行為となる。」
まず、アウラという言葉が聞き慣れないと思います。読む人によっては、「またどこぞの哲学用語が出てきたぞ。小難しい…。」とアレルギー反応が起きてしまう人もいるかもしれませんが、お付き合いください。
アウラとは、
写真人文学の文章の中では、『独特で神秘的な気運。その対象の原本や一度きりのタイミングで現れるもの。近くにありながらも近づくことのできない感覚。作品に対する主体が、その対象との関係から作られるある種の距離感。』とあります。
例を挙げます。レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザの原本はこの世でたったひとつしかありません。そして現在はルーブル美術館でしか見ることができません。ですが、その作品自体の芸術的価値を観ようと世界中から多くの人がルーブル美術館に訪れます。モナリザを観るためにルーブルに訪れることは、簡単なことではありません。ルーブルに行くまでの旅費、道のり、時間、そして行列に並んでまで見るものの価値とは何でしょうか。しかし、実際にこうした徒労のあとにモナリザを観たときの感動は計り知れないことでしょう。なんていったって、モナリザを観るためにお金を貯めて、何十時間もかけて、さらに行列に並んで、写真でしか見たことのないモナリザの本物を見るわけですから。この特別感、感動、そういったものが湧き出ること、これが、私たちがモナリザから感じているアウラです。
何百年も前に描かれた名作モナリザの本物は、まずこの世でたったひとつしかないのでその時点で希少性を感じます。そして、そのためにお金と時間を費やしてやっと観られること、つまり簡単に本物が見られないこと、これに現代人は価値を感じます。そういった外的要因をいろいろ主観や経験に植え付けたうえで観ているモナリザの価値は、何の情報もなく自分自身から純粋に湧き出る感覚というよりは、そういった前情報や苦労を身に纏ったものによるものが大きいと思います。モナリザそのものを見つめるというよりは、そこに付随する外的な要素に感動している、私にはそんな気がしてなりません。
アウラとはこういった外的な前情報やそのために費やした苦労の経験から出てくるものかもしれません。何にも知らない状態でモナリザを観て、純粋に自分だけの感性でそのものに価値を見出し感動することができるのか、私にはその自信はありません。
しかし、昔の芸術作品の基準とはそういったものでした。いわゆる古典主義的芸術的観点では、芸術であるかどうかの基準はこの「アウラがあるかどうか」でした。その「アウラがあるかどうか」の判断基準は、まず芸術作品が神の定めた美的基準を満たしていることでした。神が定めた美を再現している作品=神によって保証されている感覚を覚えます。これによって芸術作品は人の手が届かないような距離感のある感覚を人々は覚えます。また、昔の芸術作品は手作業による完全アナログなものしかありません。それによって芸術作品は言わずもがな唯一性が付随しており、そしてその時にしか現れない一回性を帯びています。その時点で希少性が生じます。よって、昔の芸術作品とは、『神が定めた美の基準を持ち、唯一無二である』ことが芸術であるかどうかの基準になります。
ですが、時代は変わります。
1900年代に入ると、科学や技術が急激に進歩します。今まで神のみぞ知る未知の領域が、人間の知識と科学により次々と明らかになります。モノを作るのも機械式となり、今まで職人が手作業で行ってきた仕事が機械にとってかわり、より正確に精密に、そして再現性が高く、人間の仕事の負担が減っていきます。1930年代になると、写真や映画が大衆の身近に存在するようになり、誰でも手軽に映画を観て写真を撮ることができるようになります。その中で多くの問われていたのが、芸術的価値の消失です。
今まで、「アウラがあるかどうか」だった芸術的価値が、写真や映画などの複製技術の向上により、誰でもどこでもみることができるようになってしまったからです。また、科学が飛躍的に向上した結果、今まで未知だったからこそ神秘的だった美的バランスがどんどん明らかになっていきます。そのため、今まで一部の神職者や権力者しか触れることができなかった芸術作品がどんどん大衆の目に触れることができるようになっていきます。そこで芸術的価値は混乱します。芸術作品と人々との距離感が狭まっていくことにより、「アウラ」がどんどん消失されていってしまったからです。そのことに多くの哲学者や批評家は悲しみます。
しかし、哲学者ベンヤミンはその「アウラの消失」にこそ、新しい芸術的価値の可能性があると提示します。その価値とは、「多くの人の目に触れることができる価値」でした。今までの芸術作品は大衆には敷居が高かったため、本当に良いかどうかの価値基準は人々ひとりひとりの主観の中にはありませんでした。そのため、芸術かどうかの価値判断に自由度は少なかったように思えます。しかし、ベンヤミンの提唱したアウラの消失によって生まれた新しい価値とは、展示さえすれば誰にでも気軽に見ることができるので、その作品の価値判断は人々ひとりひとりの主観に依る部分が大きくなることです。良いかどうかという価値判断を自分自身の感性と思考を巡らせることができる自由度を得ることができ、芸術の幅が大きく広がります。
またベンヤミンは、大衆の芸術的価値判断を「アーケード」という概念で見ることができるとも述べています。「アーケード」とは、ショッピングモールや表参道などで見るショウウィンドウのことです。そのガラス張りの空間は、現実的ですがとても理想的で私たちが憧れる世界が創られています。私たちの生きる世界に見られる服やバッグがマネキンやインテリアによってきらびやかにディスプレイされている空間は、理想的な現実でありながら私たちの日常生活と比べると手が届きそうで届かない憧れの空間であります。そのため、その空間を見ている時は、あたかも私たちがその世界にいるような幸福感に浸れますが、そのから離れると比較される実際の憂鬱な日常生活へと戻っていかなければならない。そんな一種の悲しみが漂います。それは、近代現代の社会構造が生んだ悲しみとも言えます。機械や労働力の量産化や複製化によって人間ひとりひとりの価値も唯一無二性が薄まって感じられるようになってきたとも言えます。大きな貧富の差が見えなくなり、その代わり自分がほかの人と同じように感じられる社会の仕組みの中で、慰めになるものは現実的だけど非日常間の漂う世界観なのかもしれません。
しかし、その非日常の特別感こそ次の芸術的価値なのだとベンヤミンは提唱します。アウラの消失によって芸術的作品は身近になり、人々は現実的な非日常感に身を委ねることができます。映画や写真というポップカルチャーが流行するのはそのためです。そこからベンヤミンは写真こそが近代の芸術的価値の特徴を引き継ぐ可能性があると示唆しています。

見慣れたものを見慣れたように見ない。
写真の芸術的価値とは、誰にでも手軽に撮影ができ、また複製ができるためいつでもどこでも写真を展示することが可能なところです。そして、撮影者の主観が写真に反映されやすいという特徴から、写真の中の現実世界が見たことがあるのに撮影者の視点によってどこか新鮮に見えることがあります。写真とは、写実的です。実際に存在する物しか写真の中に収めることができません。なので、写真の中に写るものは見たことのあることしかありません。しかし、撮影者の主観は一人一人違います。写真が写実的であるということは、撮影者の主観に忠実であることを意味します。撮影者の主観が被写体のどこにフォーカスしているかによって、同じ被写体を撮っても写り方は異なります。それは、撮影者の世界認識の仕方によるとも言えます。
例えば、私が目の前の猫をこの町の背景の一部として見れば、写真にはその町の背景の一部として写し出され、猫の表情や動きには着目しないかもしれません。しかし、私が目の前の猫にキャラクター性や個性を見出したら、猫を中心とした写真を撮り、町の風景は猫のキャラクター性を表すための一部の要素のとなりメインの被写体にはならないでしょう。このように、撮影者が一人一人違った人格や世界観を持っているため、写真という形式に写し出されているのは、見慣れているものだけど見慣れたものではないものになります。
このように撮影者の視点に依存する写真は、撮影者が被写体に価値を見出さなければその写真もそのように価値の見えない写真となります。ちょっと怖くないですか?少なくとも、撮影者である私には少し重く感じられてきました…(笑)。良い写真=価値のある写真=撮影者が目の前のこと一つ一つに感動している写真には、撮影者の感性の鋭さや感覚の深さが求められますし、写真のことだけでなく、自分自身のこと、人間のこと、この世界のこと、広く認識と知識が求められます。
ライフスタジオで撮影している撮影者たちは、そのライフスタジオの理念のもとすべての行動、写真の基準は「人」になります。「人」とは、この世界に生きているすべての人が基準になります。自分に合うかどうかが基準ではありません。なので、目の前にいる人が被写体である以上は、その目の前にいる人たちを基準として価値のある写真を撮ることが私たちの普段していることになります。価値のある基準とは、さきほど述べた「アーケード」のように見慣れたものを見慣れたように見ない視点だったりします。それは、お客様から見て普段見慣れている家族の姿なのに、写真を通してみると「はっ」としたりいつも見ている顔なのに見慣れない表情を見て感動をしたり、ということも見慣れたものを見慣れないように見られることによって生まれる価値なのだと思います。しかし、私たち撮影者はどうでしょうか?毎日来るお客様を1歳、2歳、3歳、人見知り、人懐っこいなどというカテゴリーや先入観にあてはめて、毎日同じパターンで撮影をし、効率的に仕事をすることが目的になっている瞬間がないでしょうか?毎日来るお客様は、毎回違う人です。年齢は同じでも、同じ人はひとりもいません。そのことを認識するかによって、被写体の捉え方が違います。その人を見つめている写真には、必ずその人自身が写真に現われます。撮影者の主観に依る写真は正直で、被写体の見つめ方が写真に現われるからです。
そのポイントは見慣れたものを見慣れたように見ないシステムを、常に発動させることが重要になってきます。個人的には、そのシステムを常に身のそばに置くには「目的を忘れないこと」だと思っています。私たちが何のために写真を撮り、私たちの写真とは何なのか、それを常に忘れないことが重要だと思っています。実際の撮影には、人見知りも、コンディションが悪い子も、とっつきづらい人も来ます。その混乱の渦のように見える日常の出来事一つ一つに、新鮮味を感じ、目の前のすべてを愛おしいと思うこと。そうすることで、少なくとも写真を撮っているときは、その被写体のために、その人を基準とした写真を常に撮っていけるのではないかと考えます。それは、私が被写体へ向けた外的な前情報や先入観によるアウラを消失させると同時に、私が実際に見て感じた視点で被写体を見つめ、写真によって被写体の存在を定義することになると思います。それが、アウラの再構成になると私個人は勝手に考えています。
アウラがあることは、今も昔も芸術的価値があると私は思います。ポイントはそのアウラがどのように作られたかに在るとだと考えています。外的に決められたアウラなのか、ここが自由に感じ再構成するアウラなのか、依存的なのか、主体的なのか、そこに人文学の入る余地があります。人間とは何かを考えたときに、自分自身で思考し行動し生きていくことだと私は思います。ここから考えると写真を撮るときにシャッターを切る行為は、非常に人間的です。自分の視点を写真に反映させるということは、自分の認識・意志を見せる人に提示し、そこに自らの責任を持つことになるからです。
だから、ライフスタジオにいるスタッフは常に人間的であることが求められます。
そのためには、見慣れたものを見慣れないように見るシステムがキーポイントになると思います。
次回は実際に撮影で撮った写真からアウラの再構成について考えてみたいと思います。
この記事をシェアする
サイト内投稿の検索







 Top
Top About us
About us Plan
Plan Coordinate
Coordinate Interior
Interior Our story
Our story Photogenic
Photogenic News
News Staff blog
Staff blog Map
Map Education
Education FAQ
FAQ