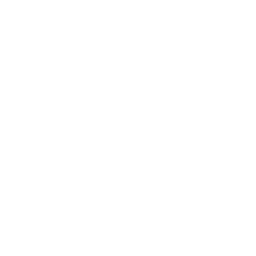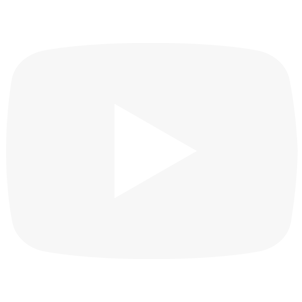Staff Blog
本社
哲学入門:第一章 現象と実在
投稿日:2011/10/17
7746 0
哲学入門:第一章 現象と実在
理性的な人なら誰にも疑えない、それほど確実な知識などあるのだろうか。この問いは、一見難しくなさそうに思えるが、実は最も難しい問題の一つである。自信をもってきっぱり答えようとしても、何かがそれを妨げている。そのことをはっきり認識するとき、私たちはすでに哲学を始めているのである。なぜなら、哲学とはこのような根本的な問題に答える試みに他ならないからだ。それも、ふだんの生活や科学的研究をするときですらしているものをすべて検討し、ふたんの考えの根本にあるあいまいさや混乱を一つ残らず見て取ったうえで批判的に答えようとすること、これが哲学だからである。
日常生活で、確実なものとして受け入れている多くのものも、吟味してみれば明らかな矛盾に満ちているのが分かる。あまりにもたくさん見つかるので、本当に信じてよいのはどれかを知るためには、かなり考えなければならないほどである。確実なものを求めるときには、私たちが現にしている経験から始めるのが自然であり、またある意味で、確かに知識はそういう経験から生み出されるものでもある。だが、直接的な経験によって知られたことに関する言明は、どれも間違っている可能性が非常に高い。たとえば、今私にはこう思える。私は椅子に座り、ある形をしたテーブルに向かい、その上には字を書いた手紙が何枚か見える。ふりかえれば窓の外には建物、雲、そして太陽が見える。私は、太陽は地球から約9300マイルのかなたにあると信じている。地球の何倍もある熱い球体であることや、地球の自転のせいで毎朝のぼり、そしてこれからも限りなくのぼり続けるであることや、地球の自転のせいで毎朝のぼり、そしてこれからも限りなくのぼり続けるであろうことも。さらには、普通の人が部屋に入ってきたら、その人は私と同じ椅子、テーブル、本、紙をみること。また、見ているテーブルは、腕を支えているテーブルと同じだということも、私は信じている。これらはどれもあまりにも明白なので、私がまったく何も知らないのではないかと疑う人にこたえる場合でもないかぎり、わざわざ言葉にするに値しないとすら思える。しかし、これらの言明はみな筋を通して疑えるので、注意深く議論を重ねないかぎり、完全に正しい仕方で言い表したことは確信できないのだ。
問題を明らかにするため、テーブルに注目してみよう。目には長方形で茶色く光沢があるように映り、触ればなめらかで、冷たく硬い。たたけば鈍い音がする。このテーブルを見、触り、その音を聴く人なら、誰でもこの記述に同意するはずだから、何の問題も起こらないと思われるかもしれない。だがもっと正確であろうとすると、とたんに面倒なことになる。テーブルは全面にわたって「本当に really」同じ色をしていると私は信じている。しかし、明かりを反射している部分は他の部分よりも明るく、そのため白く見えるところすらある。自分が動けば明かりを反射する場所が変わるため、テーブル上の色の分布も変わることも、私は知っている。ここから、人々が同じテーブルを同時に見るなら、まったく同じ色の分布を見る人はいないことになる。正確に同じ視点からテーブルを見ることができず、どんなにわずかであれ視点が変わるなら、明かりの反射の仕方も少しは変わってしまうからだ。
こうした色の違いが実生活で重要になることはほとんどないが。画家にとってはなによりも重要である。常識的に物の「本当の」色だと言われる色を、物は持つように見える、そう考える習慣を私たちは持っている。しかし画家はこの習慣を脱ぎ捨て、見えるがままの原因になる、ある区別をし始めている。「現象 appearance」と「実在 reality」の区別、つまり物がどのように見えるかと、どのようであるかの区別である。画家が知りたいのは物がどのように見えるかだが、いわゆる現実的な人や哲学者は、物がどのようであるかを知りたいと思う。しかし哲学者は現実的な人よりもはるかに強くそれを望み、また問題に答える難しさを知っているだけに、より深く悩まされることになる。
テーブルに話を戻そう。いままで分かったことから、テーブルはその色「the colour」をしていると言えるような、他からぬきんでて見える色は存在せず、テーブルのどの部分のついても同じことが成り立つのは明らかである。テーブルやその部分は、視点が変われば異なる色に見え、そのうちのどれかを他の色よりも本当であるとするり理由はない。また周知のとおり、同じ視点からですら、照明を当てたときや色盲の人、サングラスをかけた人にとっては違う色に見え、さらに暗闇のなかでは、触ったり聞いたりするかぎりでは変化していないにもかかわらず、テーブルはまったく色を持たない。つまり色は、テーブルそのものに属するのではなく、テーブルと観察者、そしてテーブルへの光の当たり方に依存するのである。テーブルのその色についてふだん話しているときには、正常な観察者が普通の視点から、通常の光の条件下で見る色を意味しているにすぎない。しかし他の条件下で見える色にも何もおかしなところではなく、本当だとみなされる資格がある。それゆえ、えこひいきを避けるためには、テーブルが、それ自体としてある特定の色をしていることを否定しなければならなくなる。
視点が違ってくるとは何が違ってくるのか?日常生活にも(視点を違うようにしてみろ?)、(目の高さに合わせないで、その対象を知ることができるだろう?)と同じ言葉をよく使う。相手が何でそうなのかわからずに、その視点で、その対象の立場で見るならば、理解が変わってくる経験をたまにする。私はさまざまな名前を持っている。世間知らずの息子、権威的な叔父、お腹いっぱいの社長、おもしろい友達…権威的でありながら常に自信が低くなろうとし、お茶を濁したりするが、時には無限の責任感で仕事をする。自信がおかれている位置で固有の目的を達成するための姿を強化する。問題はそのように自身の視点を違うように生きていきながらも、他の人に対する視点は大きく変わることは無いということだ。視点が変わらないということは、現象と実在に対して自信がどれくらい理解し、適用するかを説明している。おかれている条件と見える姿で判断することに問題が発生する。職員という現象は、今まで私達の中に内在している、[職員なら最小限これ]という固定された概念が大きな役割をしている。自身の経験から固まった洞察が、大体合理的に判断を可能にするが、それだけでは根本的な欠陥が存在している。なので、現象と実在の問題を適用することは視点を柔軟にし、そして信念を強化する役割をする。
視点に関して共に討論したい内容は[視点を柔軟にするためには何が必要なのか?]
肌理についても同じことが言える。裸眼では木目が見えるが、それをのぞけば平坦でなめらかに見える。しかし顕微鏡で見てみると、肌理が粗く、でこぼこしていたり、裸眼では見えなかったあらゆる違いが見えるはずだ。では、どちらが「実在の(本当の)」テーブルなのか。顕微鏡を通して見た方が本当の姿だと自然に言いたくなるが、もっと強力な顕微鏡が出れば、今の顕微鏡で見えている姿もまたお払い箱になるだろう。とすれば、裸眼で見えるものが信用できないのなら、なぜ今の顕微鏡を通して見たものを信用すべきなのか。こうしてこの場合もまた、はじめは信頼していた感覚に裏切られる。
テーブルの形にしても、事態はよくならない。私たちはみな、物の「実在の」形について判断する習慣をみにつけている。しかも、あまりにも無反省にそう判断するので、自分は本当の形を実際に身につけていると考えてしまう。しかし絵を描くときには習わなければならないことだが、一つの物も、異なる視点からは異なる形に見える。テーブルが「実在としては」長方形であれば、それはほとんどの視点から、鋭角と鈍角を二つずつ持つように見えるだろう。向かい合った辺が平行なら、観察者から遠ざかる方向へ収束するように、また辺の長さが等しいなら、近い方の辺が長く見えるだろう。テーブルを見るときには、普通こうしたことには気づかないが、それは、見えている形から「実在の」形を作り上げるよう経験が教えてきたからであり、生活のなかで関心が持たれるのも「実在の」形のほうだからである。しかし「実在の」形は見えるものではない。見えるものから推論されたものだ。そして見えるものは、見ている人が部屋の中を動き回るにつれ、その姿を変え続ける。すると、ここでもまた感覚はテーブルそのものではなく、その現象についての真理しか与えてくれないようだ。
人生を生きていきながら多くの経験をし、失敗の繰り返しの中で、自分独自の観念をもつようになる。[日本人はだいたい…]、[韓国人はこんな特徴が…]…実際そうだということが何回も証明され、見える現象が大体同じであり、実在すると認め、信仰に固まっていく場合がある。そうしながら私たちは[既存時代]という名札をぶらさげるようになる。上記では、実在すると信じる前に、私たちが見るものから推理されるといっている。推理されるという言葉は、確実性を内在しているが、一方では確実性に対する懐疑を持つようにする。私たちが経験し、見て触ることが推理されることだと仮定するならば、実在すると信じるということは、いつ可能になるのか?[わからない]、[知ることもできるが、わからないかもしれない]、[わかる]という多くの哲学的な主張もあり、それを始めとして種類が分かれる感じを受ける。推理から実在に対して信じる過程で各自はどんな方法を使用しているのか?相手との戦争を通して、または、自身の内面との定期的な対話を通して、感情の流れを通して…各自に質問したい。各自、どのように心理を確保するのか?
触覚を取りあげてみても同様の問題が起こる。テーブルは確かに硬さの感覚を与える。押せば、押し返してくるように感じられる。しかしそうして得られる感覚は、どれぐらいの強さで押すか、体のどの部分で押すかに左右される。したがって、体のいろいろな部分を使い、さまざまな強さで押して得られる諸感覚は、テーブルの特定の性質を直接明らかにするものとしてではなく、せいぜいテーブルの性質の記号であると考えられるにすぎない。テーブルの性質は、以上のような諸感覚すべての原因ではあるのだが。しかしそうした感覚に実際に現れることはない。テーブルをたたけば出る音には、同じことがよりあからさまに当てはまる。
かくして、もし本当にテーブルが存在するのだとしても、それは直接経験されるものと同じではなく、見たり、触れたり、聞いたりできないことが明らかになる。実在のテーブルが存在したとしても、それはけっして直接には知られず、直接しられるものから推論されなければならないのだ。ここから、非常に難しい二つの問題が同時に生じてくる。(1)そもそも実在のテーブルはあるか。(2)もしあるのなら、それはどんな対象でありうるか。
意味のはっきりした単純な用語がいくつかあれば、この二つの問題の考察に役立つだろう。感覚によって直接的に知られるもの――色、音、におい、硬さ、手触りなど――に、「センスデータ」という名を与えよう。そして、これらを直接意識している経験を「感覚sensation」と名づけよう。よって、ある色を見ているときにはいつも、その色についての感覚を持っているのだが、色そのものは感覚ではなくセンスデータである。つまり、直接意識されるものが色であり、意識そのものは感覚なのである。もしテーブルについて何かを知りうるのなら、それは明らかにセンスデータ――茶色だったり、長方形であったり、なめらかだったりする、テーブルにかかわるセンスデータ――を通じてでなければならない。しかし今まで挙げたさまざまな理由から、テーブルはセンスデータであるとは言えず、センスデータがそのままテーブルの性質になっているとすら言えそうにない。したがって、実在のテーブルがあるとすれば、それとセンスデータとの関係が問題になる。
実在のテーブルが存在するとして、それを「物的対象」と呼ぼう。よって考察すべきなのは、物的対象とセンスデータとの関係である。すべての物的対象をひとくくりにして「物質」と呼ぼう。それゆえ先ほどの二つの問題は、次のように言いなおせる。(1)そもそも物質のようなものがあるか。(2)もしあるのだとしたら、その本性は何か。
五感[our sensce]の直接の対象は、私たちから独立には存在しない、そう考える理由を初めてきっぱりと打ち出した哲学者はバークリ僧正(一六八五-一七五三)だった。彼は「懐疑論者と無神論者に反対する、ハイラスとフィロナウスの三つの対話」で、物質など存在しないこと、そして、世界を作り上げているのは、心と心が抱く観念だけだということ、この二つを証明したとうけあっている。フィロナウスはハイラスを矛盾と逆説へと追いつめ、ついには自分から物質を否定させ、それがあたかも常識であるかのように思わせてしまう。そこで使われている議論の価値はまちまちで、重要で健全なものもあれば、混乱したものや。ただのあげあし取りもある。だが、何の不合理も犯すことなく物質の存在を否定できること、そして私たちから独立に存在して物があったとしても、それは感覚の直接の対象にはなれないこと、これらを示した手柄はバークリのものである。
物質が存在するかという問いには、二つの異なる問題が含まれているので、それらをきっぱりと分けておくことが重要である。ふつうの意味では、「物質」は「心」と対しされ、空間内にあるが、そもそも何かを考えたり意識する能力を持たないと見なされている。バークリが否定するもの、主のこの意味での物質である。つまり、テーブルの存在の記号であると誰もが見なすセンスデータが、本当に私たちから独立な何かの存在の記号になっているということは、バークリも否定しない。この何かが心的ではないということ、すなわち心でも、誰かの心が抱く観念でもないことを否定しているのである。彼も、部屋を出たり目を閉じた時にも、何かが存在し続けなければならないことを認める。さらには、私たちが「テーブルを見る」と呼ぶ経験が、見ていないときにも何かが存在し続けていると信じる理由を、実際に与えるということも認める。しかしバークリによれば、この存在し続ける何かの本性が、私たちが見ているものと根本的に異なるなどということはありえない。それは確かに私たちが見ることからは独立なのだが、見ることからまったく独立ではありえないのである。こうしてバークリは、「実在の」テーブルを神の心の観念だと見なすようになる。こうした観念は、「存在し続けること」と「私たちからの独立性」という二つの要請を満たしつつ、まったく知りえないものになってしまうこともない。ここで「まったく知りえない」と言っているのは、ただ推論できるだけで決して直接意識できないという意味である。もし物質によって以上の二つの要請を満たそうとすれば、それはこの意味でまったく知りえないものになっていただろう。
バークリ以後も、テーブルが存在するためには、何らかの心――私である必要はないにせよ――が見ていなければならない(あるいは、感覚によって捉えられていなければならない)と考えた哲学者はいた。もっとも、必ずしも神の心ではなく、しばしば宇宙内の心を集めて一つにしたものだとされたのだった。そう主張する主な理由はバークリと同じで、心とそれが抱く考えや感じ以外には本当は何も存在しえない、少なくとも本当に存在するとは知りえないということである。彼らは「私たちは何かについて考えることができる。ところで、考えられている何かとは、すべて、その何かについて考えている人の心の中の観念である。それゆえ観念以外に考えられるものはない。したがって、観念以外のものは理解不可能である。そして理解不可能なものなど存在しえない」と論じて、自分の見解を裏付けようとした。
こんな議論は間違っているとうのが私の意見だ。もちろんこの議論を提示する人たちも、かくも短くぞんざいに論じているわけではない。しかし妥当であろうとなかろうと、この議論が何らかの形で提示されているのがきわめて広範に見受けられるし、またかなり多くの哲学者たち-―-恐らくは多数派といえるだろう――が、心と観念以外には何も実在しないと主張してきた。このような哲学者たちは「観念論者」と呼ばれている。彼らは物質を説明する段になると、バークリのように、物質は実は観念の集まりにほかならないと言ったり、ライプニッツ(一六四六-一七一六)のように、物質の見えるものも、実は多少発達していないところのある心の集まりだとしたりする。
しかしこれらの哲学者も、心に対比されるものとしての物質を否定するとはいえ、別の意味では物質を認める。二つの問いを立てたのを覚えているだろう。(1)そもそも実在のテーブルはあるのか。(2)もしあるのなら、それはどんな対象でありうるか。ところで、バークリもライプニッツも実在のテーブルがあると認めるのだが、バークリはそれを神の心の内なるある種の観念とし、ライプニッツは群棲する魂だと言う。ということは、どちらも第一の問は肯定し、第二の問に対してのみ常人からかけ離れた答えをするわけである。事実ほとんどすべての哲学者が、実在のテーブルがあることに同意するように思われる。つまり、「色、形、なめらかさなど、どれほど多くのセンスデータが私たちに依存するとしても、それらが生じていることは、私たちから独立な存在するしるしである。そしてそれはセンスデータとはまったく異なるのだが、しかし実在のテーブルと私たちが適切な関係にあるときには、いつでもセンスデータの原因になると見なされているものである」ということは同意されるのである。
すべての哲学者が同意するこの点――その本性がなんであれ、実在のテーブルがあるという見解――が決定的に重要なのは明らかだろう。それゆえ、実在のテーブルの本性に関するさらなる問いに取り掛かる前に、この見解を受け入れる理由を考察することは意義がある。次章ではそもそも実在のテーブルがあるとおもう理由を考えることにする。
先に進む前に、これまでに分かったことは何かを、ざっと頭に入れておこう。五感によって知られるとされる、ごくありふれた対象を取り上げるなら、次のように思われたのだった。五感が直接教えられることは、私たちから独立な対象についての真理ではなく、センスデータについての真理にすぎない。そしてセンスデータは、これまでに分かったかぎりでは、私たちと対象との関係に依存する。したがって私たちが直接に見て感じているのはただの「現象」であり、そしてそれを私たちは背後にある何らかの「実在」の記号だと信じているのだ。しかし、実在が見えないのなら、そもそも実在の有無を知る手だてがあるのだろうか。そしてもしそれを知りうるのだとすれば、実在がどんなものかを見出す手立てはあるのだろうか。
これはまったく途方にくれる問題なので、それに答える仮説がどんなに奇妙なものでも、正しくないということがなかなか示せないのである。かくして、今までまったくといってよいほど何も考えさせなかった見慣れたテーブルが、驚くべき可能性に満ちた一つの問題になる。テーブルについて分かったのは、私たちがおもっているものとは違うとういことだけだ。このささやかな成果を超えると、今のところはどのように推測しようとまったく自由なのだ。ライプニッツはそれを魂の共同体であると言い、バークリは神の心の内なる観念だと告げる。真面目な科学は驚異的であることにかけてはまったくひけをとらず、膨大な数の激しく動き回る電荷の集まりであると教えてくれる。
かくも驚くべき可能性にとりかこまれると、そもそもテーブルなど存在しないのではないかと疑いが生じてくる。このように、哲学は、望まれているほど多くの問いに答えられないとしても、問いを立てる力は持っている。そして問いを立てることで、世界に対する興味をかきたて、日々の生活のごくありふれたもののすぐ裏側に、不可思議と驚異潜んでいることを示すのである。
哲学を勉強していると、[だからこれが私たちに何の関係があるんだ?]という質問を自分にするようになる。現象と実在を区分して考えないとならず、見える現象にあまり偏りすげてもならず、その本質を見ないといけないということには同意する。しかし、少し入ってみると大体が難しい言葉が羅列されており、[何にも全てひっかけ、転ばすんだな]という考えに至るようになる。資料を探すために図書館に行ったが、関連書籍が何千冊にもなる場合の絶望的なようなものだ。このように、哲学は必要そうなので、本を開くが、少し過ぎるとその内容の難解さや肌では感じられない形而上学的な話の世界に飽きるようになる。だから、一時哲学の本を遠ざけながらも、ある瞬間に[やはり哲学が不足している]と叫びながら、再び哲学を覗くようになる。誰でも限界に到達すると基本がないと、察するようになる。基本を学ぶためにカラオケに行くわけにはいかない。ならば再び本を開きその中に必ず哲学が隠れている。
ライフサークルで哲学をする理由は何か?哲学の哲の字も知らない私が、こんな話をするのも大変申し訳ない。ライフサークルに参加する人たちにも、哲学を専攻し、今も勉強している友達にも…
結局は均衡に答えがある。日常の人生では、数多くの材料たちがお互いに複雑に絡まっている。結び目が結び目を作り、絡まっている糸巻きをほどく方法を探すのが簡単ではない。傍観と諦めの時間が過ぎ、その絡まりが私を不便にさせる。結び目を作り解く作業は同時に成されないといけない。世の中のほとんどのことは似ている。撮影も同じだ。経験から積もっていく新しい技術と共に、何故写真をするのかに対する根本的な質問を一緒にしないといけない。私達が撮影を勉強する理由も特定な目標をやれというわけではない。哲学を通して真理に接近するというよりも、日常の人生に気を起こさせるためだ。だから、些細なことにも一種の秩序を付与する力を育てるためだ。この間、あまりにもなかったために、相対的に哲学が強調されることのような錯視現象が現れる。少しずつ自身と世界に対する根源的な問いになれる必要がある。熱いブラックコーヒーに砂糖が溶けるように哲学に接しよう。
哲学は4時間割当られている。最初の1時間は、その日の内容を3分間で整理し、3回以上発表する。そして、各自の質問と意見、主題選定に1時間。残りの2時間は主題討論にする予定だ。だから、前もって3分間発表することと、各種質問を準備してくるのがよいだろう。。
この記事をシェアする
サイト内投稿の検索
- トップ
- Staff Blog







 Top
Top About us
About us News
News Our story
Our story Staff blog
Staff blog Map
Map