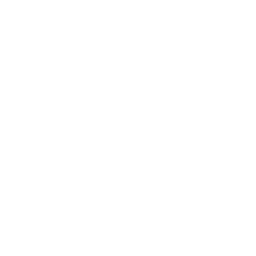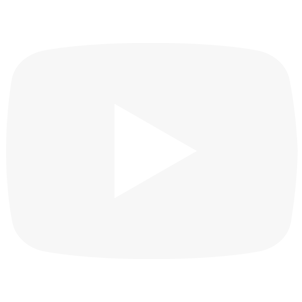Staff Blog
つくば店
MMK⑲信念に生きる
投稿日:2013/9/18
1443 4
この本はアパルトヘイト(人種隔離政策)という搾取の社会システムの悲惨さが書いてあるわけではありません。
アパルトヘイトと戦い続けるネルソン・マンデラの姿が、私たちが人生において大切にしなくてはならない原則や価値観がこの本には書いてあります。
それが、日常生活を送っている私たちが困難に立ち向かおうとするときに、どうすればいいのか?を教えてくれる本です。
しかし、この本を読んでいてアパルトヘイトが行われた南アフリカの歴史についてなにも知らなかったので、少しだけだが自分なりにまとまめてみました。
歴史を見ていくと、ある日突然アパルトヘイトが行われたのではなく、100年以上も前から人種差別による搾取があったのです。
大規模な政策とまではいかないが、本質は変わりません。白人優位となる社会システムを、どういう手段で構築していくのか?1930年から1994年まで、それだけが考え続けられてきたように感じます。
おそらく現在は、国による政策や制度による差別はないと思いますが、もしかしたら個人による差別はまだあるのかもしれません。
以下が、簡易ですが南アフリカの歴史です。
【1652年】 オランダ東インド会社がこの地に到来し、喜望峰(南アフリカ共和国南西端の岬)を中継基地とした。以後、オランダ人移民は増加し、ケープ植民地が成立した。
【1930年】 イギリスがケープ地域を奪い、イギリス人が多数移住した。
【19世紀】 金とダイヤモンドが発見されると、ケープ植民地首相セシル・ローズの率いるイギリスは、領土をさらに広げようとし、アフリカーナー•ボーア人(ケープ植民地を形成したオランダ系移民)たちと戦争の原因となる(ボーア戦争)
ボーア戦争以来、統治側のイギリス人とアフリカーナーが激しく対立し、アフリカーナーの多くは経済的な弱者となり「プア・ホワイト」と呼ばれる貧困層を形成していた。
これら白人貧困層を救済し白人を保護することを目的に、さまざまな立法がおこなわれてきた。
それが差別という名の緩和策だ。
【1911年】「鉱山労働法」人種により職種や賃金を制限し、熟練労働を白人のみに制限した。
【1913年】「原住民土地法」アフリカ人の居留地を定め、居留地外のアフリカ人の土地取得や保有、貸借を禁じた。
【1926年】「産業調整法」労使間の調停機構が設立され労働者の保護立法のさきがけとなるが、アフリカ人労働者は労働者の範囲からはずされた。このため、以後は白人の労働組合のみが労働者を代表することとなった。
【1927年】「背徳法」異人種間の性交渉を禁じた。
【1934年】 イギリス国会で南アフリカ連邦地位法が可決され、正式に主権国家として規定された。
【1948年】 アフリカーナーの農民や都市の貧しい白人を基盤とする国民党が政権を握り、アパルトヘイト政策(人種隔離政策)を本格的に推進していった。
【1994年】 全人種参加の総選挙が実施されアフリカ民族会議(ANC) が勝利。
ネルソン・マンデラ議長が大統領に就任した。アパルトヘイト廃止に伴いイギリス連邦と国連に復帰し、アフリカ統一機構(OAU)に加盟した。
マンデラ政権成立後、新しい憲法を作るための制憲議会が始まり、1996年には新憲法が採択され、国民党は政権から離脱した。
ネルソン・マンデラは1918年生まれで、弁護士として活動すると共にアフリカ民族会議(ANCHORS)に入党し反アパルトヘイト運動に取り組みます。
【1961年】 ウムコント・ウェ・シズウェ(民族の槍)という軍事組織を作り司令官になりましたが、その活動により1962年に逮捕され、27年に渡り収監される。
この27年間という長い年月の過酷な状況に耐えながら、自らの人生をアパルトヘイト撤廃に向けて実現させました。
文章で書くと、重みがあまり感じることができないのですが、自分が今ままで生きてきた時間を不自由で理不尽な刑務所で過ごしてきたことを考えるとゾッとしました。
自分だったらと考えると、いかなる理由でもおそらく耐えられなかったと思います。そう思ってしまうことが、信念がある人とない人の違いなのだと思います。
「どんな時も前向きに!!!」とよく聞くが、どういう意味なのだろう?
言葉のニュアンスは、諦めるな!とか、落ち込むな!とか、ポジティブに!ということかなと思っていました。
この本を読んで、自分の中で「前向き」がどういうことなのかを考えてみました。
辛いことがあってもただ耐えていつか忘れることが「前向き」なのではなく、辛いことを克服できる自分の行動哲学があることが「前向き」ということなのだと私は思いました。
自分にそんな時があっただろうか?と聞かれたら、耐える「前向き」はあったのかもしれません。
いつでも、どこにいても、なにをされても、本当の意味で「前向き」になることなどできるのだろうか?
大切な人が目の前にいなくなっても、誰からも必要とされることなく孤独な時も、人から、あなたはいらない、と言われても、「前向き」になどなれるのでしょうか・・・。
なぜ「前向き」になれないと考えてしまうのだろうか?
私には、二つの理由があると感じました。
一つ目が、自分の生きる目的を失ってしまったからです。二つ目が、それでも生きてく方法がわからなくなってしまった時です。
いつも同じ壁で立ち止まってしまうのは、いつも立ち止まる習慣が自分にはあるからだと思いました。
自分に甘えるからだ。負けるからだ。そう自分で選択しているからだ。
そうは分かっていても、今の自分の思考と行動を変化させて習慣化させていかなければ、本当の意味で「前向き」にはなれないのだと思いました。
信念というものはそうやってつくられていくのだと思いました。
つまり、マンデラは目的のための正しい哲学による思考と行動の習慣化を実践している人なのです。
本文中に「大きく深い悲しみでも、何も手につかなくなってしまっている人間ではないことを行動で示さなければならなかった」
「どうしようもない時ほど、何事もないように堂々とすること。恐怖心に負けることなく自分を失わない」
と書いてある通りマンデラも同じ人間であり、私たちと同じ感情を持っているのです。
しかし、いくら辛くてもただ涙を流して耐えることではなく、どのような状況でも目的のために自分をコントロールすることは忘れないのです。
そして、マンデラが偉大なのは欠点がないからではなく、自らの欠点に対して自制と克服をしたからなのです。
生涯においてマンデラは非常に多くの難しい決断を下してきました。中には、不公平な判断、時には、人を傷つけたり、人命を奪う結果になった決断もありました。
「自分が選んできた道は、本当に価値のあるものだっただろうか?」
決断をする者にとって、考えることは「選ばなかった道」のことだと思います。
誰しも「ああすればよかった。こうすればよかった。」と考えてしまう時があります。
でも時間を戻せないことはわかっています。
だから、これから自分がなにをするか?によって決断した「選んだ道」「選ばなかった道」に対しての意味が変わっていくのだと思いました。
本を読んでいて自分が敏感になる瞬間がいつもあります。それは、自分の欠点が書かれている時です。
この本で私が一番敏感になったのが「物事が進んでいくスピードよりも、物事がどこに向かっているかという方向性が大切だ」という言葉です。
すぐに結果を出そうと焦ってします自分がいます。それで本来行くべき道から外れてしまうことがあります。
人や物事のスピードにはペースがあり、自分には決められない。正しい方向性に修正していくことしかできないことを哲学として行動していければいいなと思います。
それが「選んだ道」「選ばなかった道」に意味を与えてくれることを信じて・・・・。
この記事をシェアする
サイト内投稿の検索
- トップ
- Staff Blog







 Top
Top About us
About us Plan
Plan News
News Our story
Our story Staff blog
Staff blog Interior
Interior Coordinate
Coordinate Map
Map FAQ
FAQ