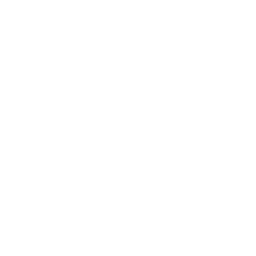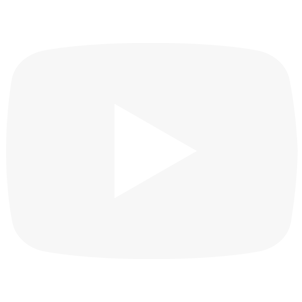Staff Blog
つくば店
mMK⑰ブルーオーシャン戦略
投稿日:2013/5/21
1720 0

ー人間は必ずイメージをもとに思考しているのだー
私は、既存の市場空間に限界があるのではないかと思い込んでいる。
現在、売買されているモノやサービス、システムには、これ以上新しい価値が生み出すことができないのではないかと思うぐらいに完璧にできている。
そう思わないだろうか?
例えば、私たちの身近にあるマクドナルド、スターバックス、ユニクロ、iPhoneを超える価値のあるものが出てくるだろうか。
いや、必ず出てくるよ。と言うことは簡単かもしれないが、ではどのような?と聞かれても想像することはなかなか難しい。
本当に懐かしい話だが、小学生の頃、CDとラジオとカセットテープの再生録音が一つの機械でできる「CDラジカセ」と、コンパクトで持ち運びができるカセットテープ再生機の「ウォークマン」という商品があった。好きな音楽やラジオを「CDラジカセ」でカセットテープに録音したものを、部屋を真っ暗にして布団に入ってイヤホンを耳にして「ウォークマン」で夜中までよく聞いた懐かしい思い出がある。
当時は、個人的な趣味をすごく身近なものにしてくれた便利な商品だった。
現在までウォークマンは時代のニーズとともに、カセットテープからCDへ、CDからMDへ、MDからデジタル携帯音楽プレイヤーへと形を変化してきた。
では、デジタル携帯音楽プレイヤーと聞いて思い浮かべるのはSonyのウォークマンだろうか?ほとんどの人がAppleの「iPod」ではないだろうか。
しかし、ウォークマンのほうがiPodよりも先に商品化しており、音楽配信サービスもあったのだ。
なぜ先手を打っていたのにも関わらず失敗したのか?
理由は、音楽配信サイトの分断と厳しすぎる著作権保護があるからだ。
レコード会社ごとに音楽配信サイトが分かれており、顧客が好きなアーティストの曲を探し回る必要のある面倒なシステムだった。そして、曲をダウンロードしてもCDーRにコピーができないし、メモリーカードへの制限転送あったからだ。つまり、いざウォークマンに曲を入れて持ち歩いて聞くためには、手間と制限がありすぎなのだ。
結局、無数にある音楽から好きなものを早く探し出す検索性に優れた「iTunes Store」という音楽配信サービスが充実していたから、私たちがウォークマンよりiPodを使っている理由なのではないだろうか。
携帯音楽プレイヤーの性能競争やマーケティング競争に正面から参入するのではなく、コンテンツ(楽曲)の権利関係に関わる問題解決こそがAppleの強みになったのだ。
つまり、ライバル企業を打ち負かそうとするのではなく、むしろ買い手や自社にとっての価値を大幅に高め、競争のない未知の市場空間を開拓することによって、競争を無意味にしたのだ。
これがブルーオーシャン戦略なのではないか。
既存の市場空間で限られたパイを多く奪い取ろうするのではなく、新しい価値を創造して競争のない未知の市場空間を開拓すること。Appleは未知の市場空間を開拓したのだ。
ただ会社が生き延びればそれでよいのであれば開拓する必要はないが、模倣ではなく自分たちの手でなにか価値を世の中に与えていきたいと思うのであれば、ブルーオーシャン戦略は味方になってくれる。
ブルーオーシャン戦略は、企業が価値を生み出すための具体的な分析と方法である。
本に書いてある分析と方法を行えば、誰でも成功するのではないか?と思ってしまうほど具体的に書いてある。
・戦略キャンパス
・四つのアクション
・アクション・マトリクス
・優れた戦略に共通する3つの特徴
・価値曲線
これらは価値と実用性、価格、コストなどの調和させ、価格と革新(バリューイノベーション)を実現するために必要なツールである。
ツールを使って自社を分析し他社とは違った価値曲線を描き、いかに低コストで実現できるかどうか?がカギを握っている。
試しに、ライフフタジオ(自社)と競合他社(写真館業界)で戦略キャンパスをやってみると、違った価値曲線を描いているのが一目瞭然であることがわかる。
もしかしたら、ライフスタジオが写真館市場に登場する前から既存の写真館業界に疑問に思っている人もいたかもしれない。
なぜ、いつも同じような撮影なんだろう?なぜ、商品を買うのに高いお金が必要なのだろう?なぜ、たくさんの商品があるんだろう?なぜ、撮影中にデジカメやビデオカメラで撮影してはいけないのだろう?
私たちは本当に顧客が期待しているサービスを誤解しているかもしれない。実は、私たちが考えているものは些細なことかもしれないのだ。
つまり、写真館はモノを売る業界ではなく、サービスを売る業界なのであるということだ。
価格や機能を武器にして顧客の理性に訴えようとする業界ではなく、スタッフ一人一人を武器にして顧客の感性に訴えかけようとする業界なのではないか。
疑問を持っていたとしても、果たして続ける意味があるのかどうか?を誰も問いたださないことがレッドオーシャンの問題である。
以前からそのような習慣だったからと、古い文化や常識に従っているだけで、結局なにも変わることのない状態が続いてしまっている。
そして、今ある環境が変えれる状態であったとしても、方法と知識が適切ではないために、結局なにかをしただけで、またいつもと変わらないもどかしい状態に戻ってしまう。
なにかを変えようとして壮大なビジョンを抱くだけではなく、目標を具体的なレベルに落とし込んでいるだろうか。
そして、従業員がしかたなく目標の実行に携わるのではなく、自分たちから進んで手を差し伸べてくれるようではなくてはいけない。
従業員たちは、慣れ親しんだ手法を捨て、仕事のやり方を変えるように求められると、必ず不安に駆られる。
上からの命令や提案の真のねらいは何だろうかと。だからこそ、戦略には公正なプロセスを踏む必要がある。
従業員が目標の策定に関わる機会。理解される説明。明快な期待内容。のプロセスである。
企業は経営トップだけで成り立っているわけでもなければ、中間管理者層だけが支えているのでもない。
経営トップから最前線の従業員にいたるまで、一人一人が重要な役割を担っている。
だからこそ、会社の経営に関心を持ち、機会が来た時に逃さない準備をしておく必要があるのではないか。
この記事をシェアする
サイト内投稿の検索
- トップ
- Staff Blog







 Top
Top About us
About us Plan
Plan News
News Our story
Our story Staff blog
Staff blog Interior
Interior Coordinate
Coordinate Map
Map FAQ
FAQ