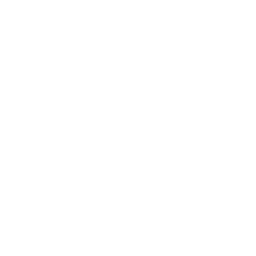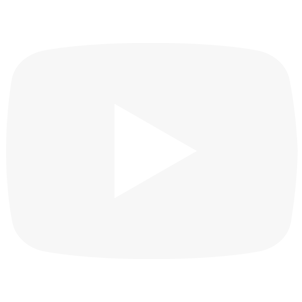Staff Blog
下関店
scrollable
音楽
投稿日:2012/12/23
1040 1

TPO
TPO
そんなことを考えながら。
「かわのさんに足りないのはフォーマルな装いです。」
と、自分自身に言い聞かせる。
と、自分自身に言い聞かせる。
そんな訳で、フォーマルは足下から!
冬らしい、ちょっと女モードなブーツを演奏会前日に購入。にも関わらず、当日は朝から大雨・・・
結局、家を出る寸前にコンバースに足を突っ込む。
あぁ。そういう運命なのですね。
なんて。
うちのTPO大臣sugawara氏にグ○チのショルダーバックを借り、極力モノトーンの装いで、これで浮かないだろうと渋谷に出動。
目指すは、初NHKホール。
日本屈指の交響楽団N響の、年末恒例ベートーベン第九のコンサートへ。そう、フォーマルな現場なのでした。
(さすがにパーカーとかオーバーオールじゃ気が引けます。)
バスケ部?とか、テニス部?とか、地黒のせいなのか、テンションのせいなのか、、、いつも部活を聞かれ、何だと思う?と聞くとそう答えられますが、、、
一応オーケストラでチェロをやってました。
(きっと、あの場所で生まれ育ってなかったらテニス部だったけど、公立で珍しいオケの学校があったので興味で入部。)
全国を本気で目指す体育会系文化部で、いつもブルースリーのTシャツでチェロを弾いてました。本気でした。
もちろん悔しいことも多かったけど、それでも音楽の魅力を感じながらみんなでひとつのことをやるということ、
勝ち負けではなく、どれだけ目標に向かって貪欲に努力して聞き手に気持ちよく聴いてもらえるか、
そういうことに、ただ夢中な毎日でした。
高校を卒業してからも短大の隣の大学でもオケをしてましたが、卒業以来まったく縁がなくなってしまい、、、
演奏会も学生やアマは聞いてはいたものの、プロオケを聞くのは今回が初めてでした。
きっかけは、とある誕生日サプライズの日。
たまたま違う道で代々木公園に向かっている時にNHKホールを通りすぎ、え、これがNHKホールなんや!ってたまたま気づき。
え!ここでN響してるんや!え!第九とか!第九とか!!!!有名なやつだ!
と急にワクワクしてしまい、すぐに高校時代の同級生の東京在住の友達(管弦楽部元部長)を誘ってからトントン拍子に事が進んだということでした。
ふたりして、開演まえからそわそわ。むしろ、聞いてないのに、行くだけで感動。
会場の匂い、雰囲気、全部が懐かしくて。
緊張感の中、ひょこひょこっと出てくる指揮者ロジャー・ノリントン氏。
そのオーラ。(黒一色のエンビではない装いにきゅんきゅん。)
乱視用のメガネを持ってきてよかったと本気で思いながら演奏が始まりました。
そのオーラ。(黒一色のエンビではない装いにきゅんきゅん。)
乱視用のメガネを持ってきてよかったと本気で思いながら演奏が始まりました。
大地に突き刺さるように降り掛かるメロディー。
晴天の空のした、平和な町に黒ずくめの装いにナイフを持っている人がいそうなメロディー。
一番気持ちいい43度くらいのお湯に浸かってる、最大限のリラックスなメロディー。
手編みのセーターを着た小人が喜んでスキップしているようなメロディー。
一心に一体となって何かを訴える喜びのメロディー。
そんな妄想が音から浮かんできて、楽しんでます。
プロの洗練された音。
演奏の合間の強弱、緩急の抑揚。一瞬の静寂。
その中での指揮者の呼吸に鳥肌が立つ。
一番大事なのは、呼吸を合わせること。
自分自身が演奏している時も、必死で呼吸を感じ、自分もトップとして必死で呼吸をして知らせて合わせて、そんなことを思い出していました。
聞き手をはっとさせる構成、メロディー。安心したかと思えば激動。ちょっと浮き足立っちゃうような部分も。
音楽を聴いていると、肖像画ではあんなに険しいベートーベンも、きっとおちゃめなんだなぁと実感。
第九は、彼の生涯にとって完成したものでは最後の交響曲でしたが、人生に希望とちょっとした笑いを盛り込んだ、きっと最後だと諦めてないものだと感じました。
あれだけの楽器を、あれだけの旋律をメロディーとして生み出すということは、どれだけの命をかけるんだろうと。
だからこそ、4楽章で構成される交響曲にわたしは魅力を感じています。
(演奏したら、それはもう遠泳並みの消耗をしてましたが。。。)
(演奏したら、それはもう遠泳並みの消耗をしてましたが。。。)
そして耳の聞こえなくなったベートーベンがこの曲に込めた、
「すべての人間が“ひとつ”になる」という願い。
日本の恒例として、なぜ年末に第九が各地で演奏されるのかが分かったような気がしました。
1824年にこの交響曲が出来てから、188年。
その頃の時代から変わらない、伝えたいことが今でも生き続けているんだと思います。
その昔。オーケストラに出会った時。
オーケストラは世界だとわたしは感じていました。
どんな楽器にも。
メロディーをひきたてる裏方に徹することもある。休む時もある。
それでも必ず、思う存分歌う場面がある。
指揮者が身振り手振り、リードしながら、目線で、いけー!って合図を出して、それに応えるように全力でみんなが奏でる。
指揮者がいないとまとまらない。オケがないと音がない。
何一つ、欠けることは出来ない。
信頼する。集中する。メロディーになる。ただ、ひとつになる。それが、最高に気持ちよかった。
わたしも昔、気持ち悪いくらい真剣に、そして気持ちのいい顔をしていたような気がします。
ノリントンさんの、肩の力が抜けて気持ちよくタクトを振りながら、オケを率いてあがっていく部分、背中から本気が沸き立つ部分、司令官のように左右に手を一直線に伸ばす部分、
演奏をまかせて自分も楽しんでいるようにも見える部分、音に合わせてウキウキ足踏みしている部分、
それが全部音につながっていて、心を越えた魂を感じる演奏でした。
本当に、行けてよかった。
老若男女、小学生くらいの子たちもいる演奏会でした。
こんなに身近にプロの演奏がある、ってすごい。
関東に出てきてから6年。
今までなんで来なかったんやろ、、、とふたりして声をそろえたり。
でも、きっと、余裕ができたんやね、おとなになったんやね、ってしみじみ。
音楽に浸りつつ、なんだか浮かれてフレンチ&ワインの店に入ったりして。
本当に、高校のオケは楽しかった。女子校楽しかった、なんて昔話に盛り上がった夜でした。
鼻歌でも、ロックでも、クラシックでも。音楽があるということ。それはどういうことなのか。
文章でも、言葉でも。
何が残っていくのか?
それは共通の想いかも知れません。
(きっと、ブルーハーツだってずっと残っていくと思うんです。)
この記事をシェアする
サイト内投稿の検索
- トップ
- Staff Blog







 Top
Top About us
About us News
News Photogenic
Photogenic Our story
Our story Staff blog
Staff blog Interior
Interior Coordinate
Coordinate Map
Map FAQ
FAQ