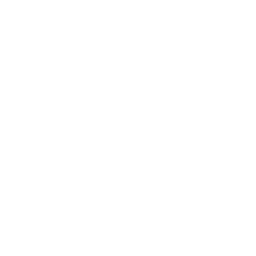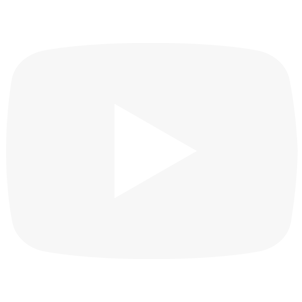Staff Blog
本社
哲学入門 第2章 物質は存在するか
投稿日:2011/11/9
1237 0
哲学入門 第2章 物質は存在するか
この章で問題にしなければならないのは、どういう意味であれ、物質なるものがあるかどうかである。ある内在的な本性を持ったテーブルが存在し、見ていないときにも存在し続けているのか。それとも想像の産物にすぎず、長い夢の中で見ている夢のテーブルでしかないのか。これはとてつもなく重要な問題である。なぜなら、対象が[私たちが知覚することから]独立して存在すると確信できないなら、他者の身体についても確信できなくなる。さらには、その身体を観察する以外に、他者に心があると信じる理由はまったくないため、他者の心についてはなおさら確信できなくなるからだ。それゆえ、もし対象が独立して存在すると確信できないならば、私たちは一人孤独に砂漠に取り残されることになるだろう――外界はその全体が夢にすぎず、存在するのは私ひとりなのかもしれない。これはあまり気持ちのいい可能性ではない。とはいえ、こんな可能性はないと厳密に証明することはできないとしても、本当に夢にすぎないと想定すべき理由もまったくないのである。なぜないと言えるのか、これこそ本章で理解しておくべきことでる。
不確かな問題にとりかかる前に、多少なりともしっかりした地点を見つけておき、そこから出発することにしよう。私たちは、テーブルが物体として存在することを疑わない。見ている間は何らかの色や形が見えていること、押している間は何らかの硬さの感覚を経験していることは疑われない。こうした心理的なことはどれも、何の疑問も呼び起こさない。それどころか、他に何が疑えるにせよ、私たちの直接経験のうちの少なくともいくつかは絶対に確実だと思われる。
近代哲学の創始者であるデカルト(1596−1650)は、今でも有益な方法を創造した。体系的懐疑の方法である。きわめて明晰判明に正しいと分からないものは、何も信じるまい、疑わないでいる理由が見つかるまでは、疑えるのなら何でも疑おう、彼はそう決心した。この方法を使うことで、存在することが絶対に確実なのは自分自身だけだと、デカルトはしだいに確信するようになった。デカルトは、「人を欺く悪霊が、本当は存在しない物を私の感覚に映し出し、次々と知覚させているのではないか」と想像した。そんな悪霊が現実にいる可能性はきわめて低いが、ないわけではない。それゆえ感覚によって知覚される物は疑うことができる。
体系的懐疑
体系・・・哲学全体は一本の木に例えられ、根に形而上学、幹に自然学、枝に諸々のその他の学問が当てられ、そこには医学、機械学、道徳という果実が実り、哲学の成果は、枝に実る諸学問から得られる、と考えた。
方法・・・ものを学ぶためというよりも、教える事に向いていると思われた当時の論理学に替わる方法を求めた。そこで、もっとも単純な要素から始めてそれを演繹していけば最も複雑なものに達しうるという、還元主義的・数学的な考えを規範にして、以下の4つの規則を定めた。
- 明証的に真であると認めたもの以外、決して受け入れない事。(明証)
- 考える問題を出来るだけ小さい部分にわける事。(分析)
- 最も単純なものから始めて複雑なものに達する事。(総合)
- 何も見落とさなかったか、全てを見直す事。(枚挙 / 吟味)
方法的懐疑・・・幼児の時から無批判に受け入れてきた先入観を排除し、真理に至るために、一旦全てのものをデカルトは疑う。この方法的懐疑の特徴として、1つ目は懐疑を抱く事に本人が意識的・仮定的である事、2つ目は一度でも惑いが生じたものならば、すなわち少しでも疑わしければ、それを完全に排除する事である。つまり、方法的懐疑とは、積極的懐疑である。―――――引用文
だが、自分自身が存在することは疑えない。なぜなら、デカルト自身が存在していなければ、いかなる悪霊も彼を欺けないからである。デカルトが疑っているのなら、彼は存在しているにちがいない。内容が何であれ、デカルトが何かを経験しているかぎり、彼は存在するはずだ。こうして、自分が存在することは、デカルトにとって絶対に確実だったのである。彼は「われ思う、ゆえにわれ在りCogito ergo sum」と言い、この確実さを基にして、彼が疑いによって荒廃させた知識の世界の再建にとりかかる。懐疑の方法を想像したこと、そして主観的なものこそ最も確実だと示したことにより、デカルトは哲学に大きな寄与をなした。現在でも哲学を学ぶ人すべてにとってデカルトが有益なのも、このためである。
しかし、デカルトの議論を使うには注意しなければならないことがある。確実性を厳密にとるなら、「われ思う、ゆえにわれあり」は余分なことまで言っている。昨日と今日とで自分は同一の人物だと私たちはかたく確信しており、またある意味でこれは疑いなく正しい。しかし実在の「本当の」自我は、実在のテーブル同様到達しがたいもので、一つ一つの経験に備わる、絶対的で納得せざるをえない確実性を持っているようには見えない。テーブルを見つめて茶色が見えているまさにその時、きわめて確実であるのは、「私が茶色を見ている」ではなく「茶色が見られている」である。もちろんこれは、茶色を見ている何か(あるいは誰か)を含んでいる。しかし「私」と呼ばれている、多少なりとも存在し続けている人物を含んでいるわけではない。直接の「経験が持っている」確実性が示すかぎりでは、茶色を見ているものがきわめて刹那的で、次の瞬間に別の経験をする何かと同一ではない可能性が残る。
したがって、ひとつひとつの考えや感じこそが最も根底的な確実性を持っているのである。そしてこのことは正常な知覚だけでなく、夢や幻覚についても言える。つまり、夢や幽霊を見ているときにも、自分が持っていると思う感覚を、私たちは確かに持っている。たださまざまな理由から、その感覚に対応する物的な対象はないと考えられるのである。それゆえ、自分の経験に対して、確実な知識が持てる範囲は制限されてはならず、例外なく確実に知られると認めるべきなのである。よって、どのように役立つかはともかく、知識の探求を開始するためのしっかりした地盤がここに手に入ったことになる。
すると、考えるべき問題はこうなる。自分が持っているセンスデータを確信しているとして、そのセンスデータはそれとは異なる何かが――「物的対象」と呼べるものが――存在するしるしだとする理由はあるだろうか。テーブルと結びついていると見なされるのが自然なセンスデータをすべて数え上げたとき、テーブルについて言うべきことは何も残っていないのか。それとも、まだ何か残っているのか――つまりセンスデータではない、部屋を出た後でも存在し続ける何かが。常識はためらうことなく「残っている」と答える。センスデータをただ集めただけの物は、売買したり、乱暴に扱ったりテーブルクロスをかけたりできない。クロスがテーブルをすっぽりと覆ってしまったら、テーブルからはセンスデータがまったくえられなくなる。それゆえ、もしテーブルがセンスデータに他ならないとすると、テーブルは存在しなくなり、クロスは奇跡的に、以前テーブルがあった位置に浮かんだままだということになる。これは明らかに常識に反している。もっとも、哲学者たらんとするもの、非常識なことに臆するようではならないのだけれども。
センスデータだけでなく、物的対象の存在もしっかりと認めておくべきだと感じるのは、誰に対しても同一の対象がほしいということがその大きな理由の一つである。十人で食卓を囲むとき、その人たちは同じテーブルクロス、ナイフ、フォーク、スプーンを見ていないと主張するのは馬鹿げているのではないか。しかしセンスデータは各人に私的である。誰かの司会に直接立ち現れているものは、その他の人の視界には直接立ち現れない。彼らはみな少しずつ違った視点から物を見ているので、物は少しずつ違ったように見えている。それゆえ、公共的で中立的な対象があるはずであり、そしてそれが複数の人によって何らかの意味で知られるのだとすれば、各人に現れる私的な個々のセンスデータに加え、さらなる何かがなければならない。では、そういう公共的で中立的な対象を信じるべき根拠が何かあるだろうか。
真っ先に自然に思い浮かぶのはこういう答えである。「人それぞれ、少しずつ違ったようにテーブルを見ているとはいえ、それでもそのとき見えているものは大体似ている。また、見えているものの違いは遠近法と光の反射の法則にしたがって起こる。だから各人の持つすべてのセンスデータの基礎となる、存在し続ける対象にはたやすく到達できるのである。私は、この部屋に以前住んでいた人からテーブルを買った。彼が持っていたセンスデータは、彼が部屋を出たときに消滅したので買えなかったが、しかしそれと大体似たセンスデータを持てるだろうという、満たされる可能性のかなり高い期待は買うことができたのであり、また実際に買ったのである。それゆえ、各人が大体は似たセンスデータを持つこと、そして時が変わっても同じ場所にいるなら、持っているセンスデータは似ていること、この二つの事実によって、センスデータだけでなく存在し続ける公共的な対象があって、その時その時に各人が持つセンスデータを支え、センスデータの原因になっていると考えられるようになるのだ。」
しかしこうした考えは、自分以外にも人がいるという想定に頼っている以上、今まさに問題にしていることの答えを先に決めてかかっている。他者が私にその姿をあらわすのは見た目や声など、何らかのセンスデータを通じてである。それゆえ、もし自分のセンスデータから独立に物的対象が存在すると信じる理由が何もないから、自分の夢の一部ではない他者が存在すると信じる理由もないはずだ。したがって自分のセンスデータから独立に対象が存在するに違いないことを示すためには、他者の証言には頼ることができない。その証言自体がセンスデータからできており、センスデータが自分とは独立に存在している物の記号になっているならば、他者の証言は他者の経験が存在することを明らかにしないからである。それゆえできることなら、混じりけのない私的な経験の中に、自分とその私的な経験以外の物がこの世にあることと示す特徴を、あるいは示すための手がかりになる特徴を見つけなければならない。
自分とその経験以外の物が存在していることは、ある意味では、決して証明できないと認めざるをえない。私自身とその考え、感情、感覚から世界は成りたっており、それ以外はすべて幻に過ぎないと仮に考えたとしても、そこから論理的な不都合は何も帰結しない。夢の中で非常に込み入った世界が立ち現れているように思えても、目が覚めると思いちがいだと分かる。これはつまり、ふつうセンスデータからは対応する物的対象が推論されるのだが、夢のセンスデータはこの対応を持たずに現れることがわかったということだ(物的な世界の存在を受け入れるなら、確かに夢のセンスデータにも物的な原因が見つかる。たとえばドアのバタンバタンいう音が原因となって、海戦に参加している夢を見ているのかもしれない。しかしこの場合、物的な原因があるとしても、現実の海戦と同じ仕方でセンスデータに対応する物的対象は存在しない。人生全体が夢であり、その中で出会う対象はすべて自分で作り出したものだと想定することは、論理的に言って不可能ではない。しかし論理的に不可能ではないとしても、正しいと想定すべき理由もまったくないのである。それどころか、日々の生活の中で起こる諸事情を説明する手段としては、人生全体が夢だという仮説は、私たちから独立に対象が本当に存在し、それが私たちに及ぼす作用こそ感覚の原因なのだとする常識的な仮説に比べ、単純さでは劣るのである。
物的対象が本当にあると想定することで、どう単純になるのか、それを理解するのは簡単だ。猫が部屋の隅にいるのを見て、そのしばらく後に別の隅にいるのを見るなら、ふつうはその間のすべての地点を通って移動したのだろうと考える。しかし、もし猫が一組のセンスデータにすぎないのなら、私が見ていなかった所には猫はいなかったことになる。それゆえ、見ていない間は猫は存在せず、突然別の隅に出現したのだとしなければならない。他方、私が見ていようがいまいが猫は存在するとすれば、食事と食事の間に猫がどのように腹をすかせるかは、自分の空腹の経験からたやすく理解できる。しかし見ていない間は存在しないとすると、「存在しないにもかかわらず、その間に、存在しているときと同じ早さで猫に食欲がわいている。」というおかしなことになるだろう。さらには、私のセンスデータになりうるのは私の空腹だけだから、猫がセンスデータの集まりに過ぎないなら、猫は腹をすかせられない。それゆえ猫を提示するセンスデータの振る舞いは、ただの色片の移動と変化とみなされ、説明がしがたいものになる。空腹の表現とみなせるならきわめて自然な振る舞いに見えるのだが、ただの色片には腹はすかせられない。それは三角形にはフットボールができないのと同じことだ。
だが、猫の場合がいくら難しいと言っても、人間の場合に比べればたいしたことはない。誰かが話すとき――つまり、自分の考えや感じを結びつけているのと同じような音を聞き、同時にある種の唇の動きや表情を見るとき――聞いているものが思考の表現だと思わずにいるのは難しい。自分が発する場合には、その音は思考を表現していることを知っているからだ。もちろん夢の中でも同様のことは起こり、間違って他人がそこにいると思うこともある。しかし夢は、大なり小なり「目覚めている」間の事柄にうながされて起こるものであり、また物的世界が本当に存在することを受け入れるなら、科学的原理によっておおよその説明がつけられるものでもある。したがってどのような場合を想定したとしても、単純さを原理とするなら、自分自身をそのセンスデータだけではなく本当に対象は存在し、私たちが知覚せずとも存在するものだという自然な見方を取るようになるのである。
もちろん、私たちは議論を通じて、自分から独立な外界があると信じるようになるのではない。自分の考えをふり返るようになったときには、すでにそう信じている自分に気づく。つまりそれは本能的信念だと言えるだろう。この本能的信念は、次の事実がなかったとしたらまったく疑われなかったに違いない。それは、「少なくとも視覚の場合には、センスデータそのものが独立な対象であるかのように、本能的に信じられるのだが、しかし議論を通じてセンスデータと独立な対象は同一ではありえないことが示される」という事実である。だが、たとえこのような事実を発見したとしても――ちなみにこの事実は、味やにおいに、音の場合には少しも逆説的ではなく、触覚の場合にわずかにその気があるだけだ――センスデータに対応する対象があるという本能的信念は一向に弱まりはしない。この信念は何の問題ももたらさないばかりか、かえって経験の説明を単純かつ体系的にするので、それを否定すべきだとするまともな理由はないと思われる。それゆえ、わずかに夢に基づく疑いが残るものの、外界は本当に存在し、知覚され続けることにはまったく依存せず存在し続けると認めてよいのである。
この結論を手にするために使った議論は、期待されたほど強力ではない。それは否定できないが、しかしこれは哲学的議論の典型とも言えるものなので、この議論が持つ一般的な特徴と、その妥当性は一考に値する。本能的信念に基づかなければいかなる知識も成立せず、それゆえ本能的信念を拒否すれば後には何も残らない。ここまではよいとしても、本能的信念の中には、信じられている強さに違いがある。さらにその多くは習慣や連想を介して、本能的ではない信念――しかし間違って本能的だと思われている信念――とからみあっている。
哲学は、最も強く抱かれている本能的信念から始め、ひとつひとつ取りだしてはそこから余計な混ざりものをそぎ落としながら、本能的信念の階層構造を示さなければならない。そして最終的に提示される形式では、本能的信念は衝突しあわず、調和した体系をなすことを示さなければならない。他と衝突するということ以外に本能的信念を退ける理由は受け入れるに値するものとなる。
この本能的信念とは何なのか?
本能的信念にたどりつくためにはどうしたらよいのか?
なぜ本能的信念がそこまで大事なのか?
無論、私たちの信念が一つ残らず間違っていることもありうるのだから、何を信じるにせよ、少なくとも一抹の疑いは持つべきだろう。しかし、ある信念を拒否する理由になりうるのは、他の信念以外にない。それゆえ、誤りが残っているかもしれないが、信念の相互関係と前もってしておいた批判的吟味によって、知識の体系に誤りが残っている可能性を減らし、秩序ある体系を組織することができるのである。しかもそれは、基礎となるデータとして本能的に信じられることだけを認めるような体系である。そのためには、本能的信念とその帰結を整理し、それらを改めたり捨てたりしなければならない場合に一番そうしやすいのはどれかを考えればよい。
少なくともこの役割なら、哲学は果たすことができる。大半の哲学者は、正しいかどうかはともかくとして、哲学にはこれ以上のことができると信じている。哲学が、そして哲学だけが、統一された全体としての宇宙に関する、そして根底的な実在の本性に関する知識を与えることができるのだと信じている。これが正しいにせよ間違っているにせよ、今まで述べてきたもっともつつましい役割なら哲学は確かに果たせるのであり、いったん常識の妥当性を疑い始めてしまった人に、哲学の問題が含んでいる骨折り仕事を納得してもらうにはそれで十分である。
この記事をシェアする
サイト内投稿の検索
- トップ
- Staff Blog







 Top
Top About us
About us News
News Our story
Our story Staff blog
Staff blog Map
Map