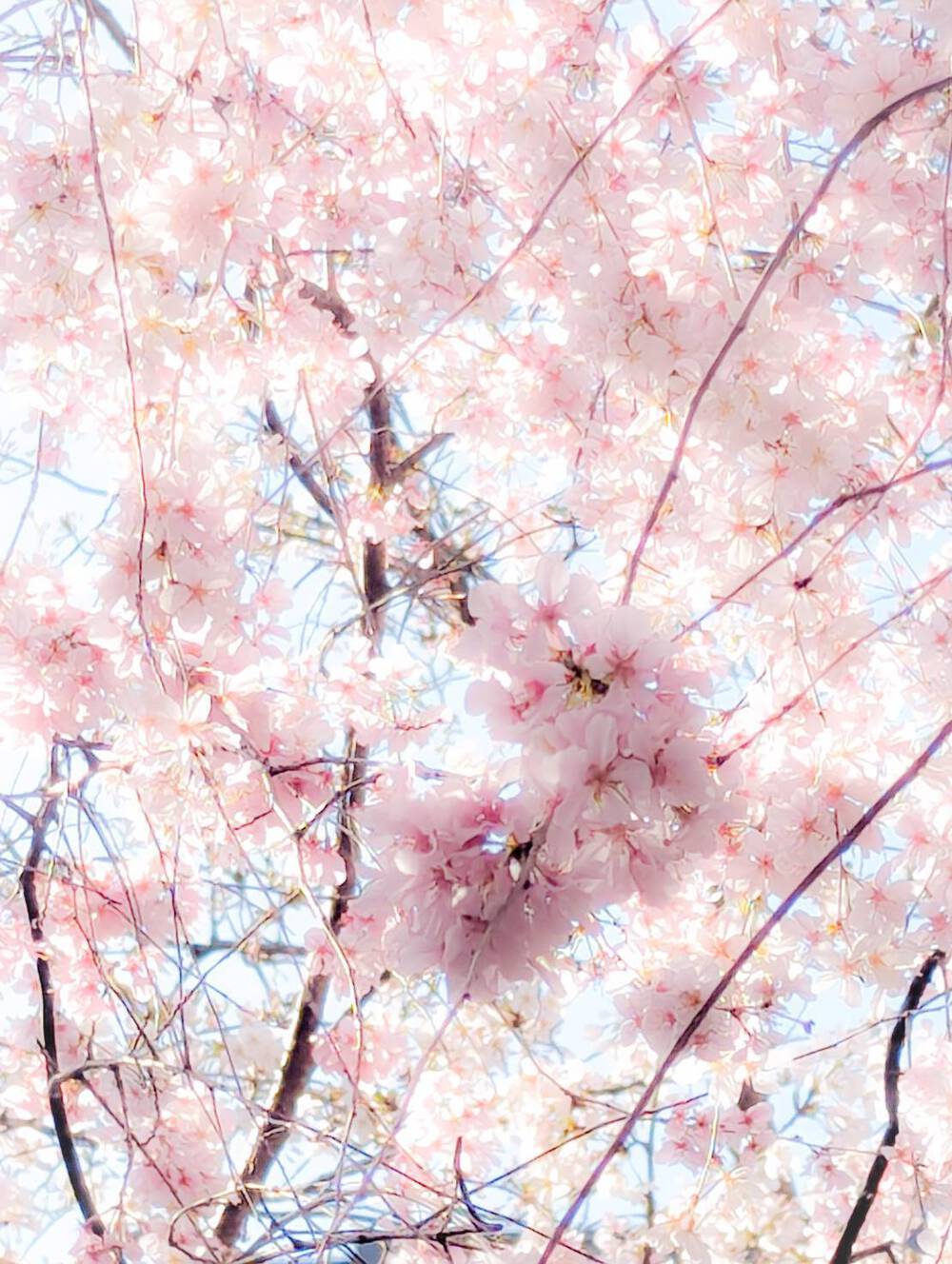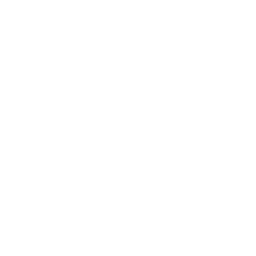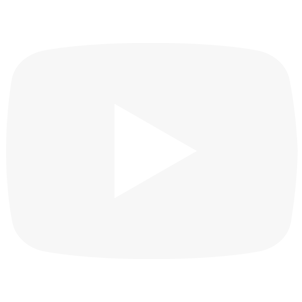Staff Blog
京都桂店
scrollable
写真人文学:隠された存在の本質②
投稿日:2017/9/14
2697 1
 ①の続き…
①の続き…◆写真は芸術になれるのか?
ハイデガーの「道具」と「作品」の考え方から、事物の制作の意図とその対象を見ている人が何を受け取り何を見るか(または経験するか)で、
その事物が「道具」になるか「作品」となるかの存在が決まります。
つまり、絵や彫刻はそもそも作成者の意図がその作品の「存在の顕示」であることから、作品であると規定したわけです。
作成者の意図がその作品の「存在の顕示」であり「何かしらの真理の顕示」であり、見ている人がその人の主観からその作品の「存在」を見出すことが、
芸術作品であるということですね。
では写真もそうなりえるのではないか?と個人的には思っていましたが、文章中では、ハイデガーの芸術になるのは難しいとありました。それはなぜか?
ハイデガーは、写真は複製の技術の道具だから、再現の手段だから、絵のように本質を表現することができないと言いました。
これはどういうことかというと、絵や彫刻は、作成者の意図で現実離れしたことでも空想でも幻想でもいくらでも世界を広げて描くことができます。
その存在の本質を、作成者の意図で表現する幅が広いのです。そして、その作品自体には道具のように何が役割を強いられることもない。
ただ存在を顕示するだけの自由な存在。
それが、芸術作品なのですが、写真という特性は(特にハイデガーの時代では)、現実に在るものを複製したり再現したりする道具であるという意図が撮影者にはあります。
そのため、その存在自体が道具というものから縛られ抜けられないということなのだと考えます。
また、写真は何を表現しようとしても徹底して被写体が物理的に実在するものであることから、何かを創りだすということがメインの目的にならず、
要は現実世界の再現という特色が色濃く付いて回ります。そのため、そのまま写しだすという点がメインの目的の道具という概念から抜け出すことができないのです。
つまり、ハイデガーは道具ではその物の存在の深さが無いと見なし、これ以上存在を引き出すことはできないと言っているわけですね。
その深さとは、第1章でも出てきた「アウラ」なのではないかと思います。
簡単に整理すると、ハイデガーは芸術とは「アウラ」から「存在」を生成することであり、道具には「アウラ」を出せないので
「存在」が用途や目的以上のものを引き出せないから、道具は作品にはなり得ないということなのですね。
文章の下りで、ロトチェンコの試みは、写真を複製の技術として使おうとした点と社会主義国家の建設という目的に使われる道具という点で
ハイデガーによって否定されえてしまいますが、存在の本質まではいかないにせよ「何かを顕示しよう」とすることが、芸術になるのではないかという主張をされています。
特にロトチェンコの時代は、ソビエトが多大なエネルギーのもと全体主義国家だったわけで、その社会の中に住んでいたロトチェンコは革命意識に溢れていたと。
そこで芸術と人生が一致していた人の身になってみると、写真は目的達成の道具でありながらも何か自分の追い求めた理想を表現するものであったというわけです。
それって、芸術なのかもしれないって私も思います。
つまり、ハイデガーが規定した厳格な芸術作品への定義が時代によって変化し、すべてがハイデガーの基準に当てはまるわけではないのではないかというわけですね。




社会主義的革命家であったロトチェンコは、芸術の在り方自体はハイデガーと大きく変わらず写真自体を本質と見ていたので、
今まで権威のある者やブルジョア達の領域であった芸術でしたが、写真がその対象になることで大衆に転移されることを望んでいました。
文章の中で、「主体的インスピレーションを吹き込んだ芸術を、ブルジョア的だと貶めていた」とありますが、それは創作の空間を生成することが、
大衆には時間的にも経済的にも難しいので、芸術の持つ素晴らしい意義をブルジョアしか持てないことに反発したからです。
芸術作品を創作したり鑑賞したりすることによる人間的な思考の営みを、大衆に転移することで人間全体がより良い人生を送りより良い社会になるのではないかというロトチェンコの考えから、彼は見慣れないようにしてアウラを再構成するという表現方法で、作品を生産することを選んだということになります。
ジョージ・オーウェルの「全ての芸術は宣伝である」という言葉は、近代社会での芸術の在り方を表しています。
宣伝は、商品であれお店であれ社会の政策であれ、その目的は「そのものが何か?」であり「そのものが良い」」ということであり、「そのものの存在を主体的に表す」ということです。
それは、芸術作品でいうところの「存在の顕示」と、同意語になるのかもしれません。
ミュシャと同じで宣伝に使われる媒体は「道具」なのかもしれません。
しかし、芸術作品も、「それ自体に何の目的も持たない」と言っておきながら、おそらく目的は「存在と真理の顕示」です。
そうなのであれば、私には全ての事物が人間によって道具になりそうな気もしてきました…。(笑)
それは言い過ぎかもしれませんが、なんにせよハイデガーの古典主義的な主張も普遍的ではないようです。
北朝鮮の「将軍様」の例もありますが、複製を通してにせよ、本質を表すアウラは発生することになっているからです。
さて、ここで再度「アウラ」が出てきます。「アウラ」はそのものが持つ独特な気運であり、近寄りたくても近寄りがたいものというのは第1章で出てきましたね。
人は、権威や宗教的なアウラを人為的に作ってきました。「将軍様」の例は、「アウラ」を利用して人々を統治している最適な例です。
文中で、「それがどんな方法で作動しても、その全てが脱人間的であるという事実である。人間はその中で従属している存在であるだけだ。」とありますが、
これはどういうことかというと、「アウラ」が発生しているといいうことは、自分と対象の間に距離感が発生していることになります。
その距離感は、「自分とは同等の存在ではない。自分では適うことのない。自分とはかけ離れた存在」として見ることだと思います。
同等である存在を見るときは、当たり前のように見えて見慣れているので「アウラ」が発生することはあまりないと思います。
しかし、先ほどの「将軍様」の例も、「神の領域」であるものを見るときも、「なにか凄い」と感じるものを見るときは、
「自分とは同等ではない=同じ人間とは思えない」ということで「脱人間的」なんだということです。
そしてその脱人間的であることから、人はその「アウラ」が発生する対象の中で従属しているというわけですね。
王様や神様はわかりやすいですがいささか現代的ではないので、例を挙げてみましょう。
今、私たちは資本主義社会に生きています。
その中では、すべての基準が通過なので、お金が無いと食べ物も何も手に入れることができませんし、生活を維持するにはお金が必要不可欠です。
だから、私たちは就労して生活するためのお金を自分で稼がなくてはいけません。
しかし、自立して経済活動をするには初期費用と知識が必要なため、普通の人には難しく感じるので、企業に自らの身体を資本として貸し出し、
貸し出した身体と時間を使って仕事をしてその見返りとして高くはないけれど安定的な給料をもらいます。
そうして、一生のうちのほとんどの時間を使って肉体を貸し出し続けなければ生きていけないという錯覚を起こしながら一生を過ごします。
政府も、資本主義社会だから経済が基準となります。経済を中心とした政策を作り、国民にも通貨が基準という思い込みを作るための教育をし、
かなわないくらい遠い理想を掲げ希望を失わせないようにします。外交もなるべくお金を多く生むことを基準とした選択をします。
そうした「資本主義」というアウラを発生させて、それに疑問を持たず、ただそれに隷属して生きています。
「資本主義社会」という「アウラ」も現代の人為的アウラと言えるのかもしれませんね。
歴史的に見ても、社会とは形が変われども「アウラ」を形成しながら時空を作動させているのかもしれません。
時間と空間の中で、その時代の流れや変化に適応しながら、脱人間的な中で比較をしながら人間は自分を人間的であると自覚するのかもしれません。
そうであるならば、文中で筆者が説いたように時間と空間が解体したら世界が解体するのか?
実際そんなわけあるかと思いますが、そうではない根拠はどこにもないので、なぜそんわけないのかこれもまた疑問ですね…。
「存在することは消えるが、目に見えないからと言って消えたわけではない」と言ったアッタ・キムという写真家がいます。
時空の解体とは、つまり瞬間的で流れてしまう過去のことです。時代の流れを見ると、人の社会の在り方や、体制の変化、人自体の存在意義も変わっていきます。
記憶も、何もかも流れていく時間と空間の中で、残るものは何か?その中でも変わらないものは何か?
アッタ・キムはそれを真理として見たのでしょうか?
ニューヨークという人や時間の流れが早い場所で8時間露光をして人がいたはずなのに消えてしまった場所を写しだして何かを見出そうとした彼の試みは、
ハイデガーの内容の結果物としての存在という考察に忠実ということなのでしょうか。
「その存在は消えてしまっても、目に見えないものは存在する。」その目に見えないものが、まさに「存在」なのではないか、
というのは先ほどの「存在者」と「存在」の概念ですね。ハイデガーは、その事物を見て自分が何を感じようとも変わらない「存在者」と、
その事物を見て何が自分の中に発生して残るのかということから生まれるその事物の意義である「存在」の間で人は生きているということを示唆しています。
アッタ・キムは、そのことをハイデガーが芸術作品になり得ないと言った写真が持つ特色を使って表そうとしていたのかもしれませんね。

しかし、ハイデガーの言う写真の限界を彼が超えたわけではないと文中では述べられえています。
それは、やはり写真の根本は、時間と空間と事物の再現ということだからですね。
その事物に息を吹き込むには写真自体にその力は無く、無から有を生み出せるわけでもない。
ただ、在るものを撮影者の意図で切り取って意味付けはできても、そのものの存在をそうなるように変えることもできない。
写真が何かの本質を持つものにもなれない。そういったことから芸術作品にするにはまだ足りないということですね。奥が深い…。
撮影者が直接介入することができないので、ハイデガーが写真を再現の領域と言ったわけですね。
なるほどと思う反面、疑問なのが、被写体に直接介入はできないかもしれないけれど、関与することはできますよね。
例えば、人を撮影するときは被写体と話したりお願いしたり、時には被写体から撮影者自身が何かを受け取ったりすることがあります。
ライフスタジオでもそういった経験があります。
ハイデガーの言う芸術はあくまでも、真理を何かしら生成することにありました。
それは、一人だけでしかなしえないものなのでしょうか?写真の可能性はここにあると思います。
実際に目の前の被写体をどうこうすることはかないませんし、直接介入して存在そのものを変えることはできませんが、
撮影者が既に在る被写体から何かしらを感じて、または撮影者自身が真理になり得るものを表現しようとすることで、
被写体に関与して撮影者と被写体で一つに作品になり得るものを作れるのではないか、と私は思っています。
芸術というものは、いつも否定し、否定されて、変化の中に何か普遍的なものを見出しそうとするものです。
それは結構人間の在り方にも似ていると思うのです。芸術はいつだって人の手によって生み出されていくものというのも納得ですね。
と、長々と解説をさせていただきましたが、次回の写真人文学は、こういった概念とライフスタジオの写真がどう関係しているのか考えてみたいと思います。
この記事をシェアする
サイト内投稿の検索
- トップ
- Staff Blog
- トップ
- スタジオ紹介
- 京都桂店
- スタッフブログ
- Satsuki Kudo
- 写真人文学:隠された存在の本質②







 Top
Top About us
About us Plan
Plan FAQ
FAQ Coordinate
Coordinate Interior
Interior News
News Map
Map Staff blog
Staff blog Our story
Our story