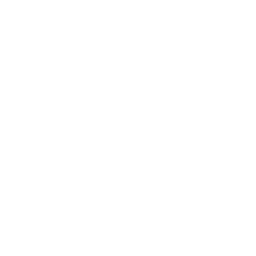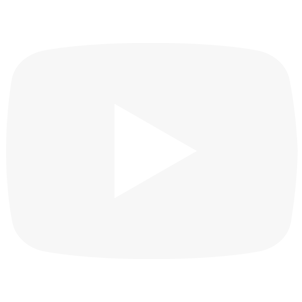Staff Blog
越谷店
アルゼンチンババア よしもとばなな 静岡プロジェクト14
投稿日:2011/11/12
1154 0
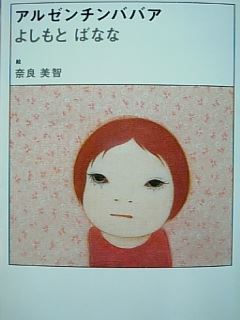
アルゼンチンババア
著者:よしもとばなな
Center:蒔田高徳
うちの妻が作者の大ファンであり、けっこうな数の書籍がうちの本棚にある。作者の文章はとても女性的で、読めば「よしもとばなな」だなといつどの本を読んでもそう思わせる。サザンオールスターズが何を歌ってもサザンオールスターズであるように、よしもとばななの世界はよしもとばななだ。タイトルが強烈だで目をひく。子供のいたずらで呼ぶようなあだ名だ。実際小説の中でそのとおりである。昔、自分の町にも必ずそういった人がいなかっただろうか。小学生の頃は、少し変な人を見ると「魔女」だとか、どうやらあの家にはおばけが出るらしいとか、勝手なあだ名をつけてみたり、いたずらをしたりする。アルゼンチンババアは、街はずれに廃屋みたいなビルがあり、そこに昔からひとりですんでいた。そのビルはアルゼンチンビルと呼ばれ、そこに住んでる外国人風のおばあさんをアルゼンチンババアと呼んだ。
主人公の母が一番最初のページで亡くなることから始まる。そして、墓石職人の父が母の死から逃げ、その理由も娘はなんとなくわかっていて許しはしていたが、まさか同世代の街の皆からアルゼンチンババアと呼ばれた人と父が一緒になっていると聞かされてしまうのだ。主人公はアルゼンチンババアに勝手な偏見を持っている。父が一緒になるのかを確かめる為に、彼女はビルに忍び込み、アルゼンチンババアと父に会う。母を失った父の心を理解する娘と、父と一緒になるようになったアルゼンチンババアが主人公の家族になっていく。物語自体は、ジブリアニメを見ているかのようなスピードで、物語の余韻を残しながら終わる。彼女の文体が人を不思議な感覚にさせるのは日本語のマジックだろうか。
この本を読んで、思い出すのは李社長との出会いだ。あの時は私は22歳くらいだっただろうか?奈美さんに成人式に写真のモデルをやってほしいと電話をもらって、自分も20過ぎてますけどモデルなんてやっていいんですか?背も低いのに・・となんだかうれしくなって、初めて向かう千葉の木更津に向かった。初めて向かうからかすごく遠い旅だった。撮影の前に、社長を紹介するねと言われて連れて行かれたアパート?ビルから現れた社長はドアを開けた瞬間、目つきが重いまぶたを半分閉じながら今も相変わらずのあの目線のアン?と言ういつもの感じで、前夜に寝てなかったのか、たくさん酒を飲んだのか、とにかく目が真っ赤で初対面の印象は・・・「奈美さんこの人本当に大丈夫?」という強烈な印象だったのを覚えている(笑) そこから木更津の写真館に行き、着物を着て写真を撮ったり、倉庫の一角でちょっとかっこいい自分でないような写真を撮ったりしてその写真の出来を見ながら「あ、この人不思議だけど、なんかすごい人なんだ」と最初に見ていた偏見が少し解けていった。なぜか、韓国語がすごく聞き取れなくて、奈美さんに「あの人、訛りがすごいですね」と言ったら「ソウルの人だよ」と言われたり。いろんな事を小説から思い出すものだ。
その思い出す感覚が、この本の中で主人公がアルゼンチンババアと偏見から、何気ない会話と時間を重ねていく中で、その距離を縮めていく内容と思い出がシンクロしていた。
それでも、妻との結婚から入社するまで、社長と接するまで偏見という文字のとおり偏っていたものだったが、最近ではようやく少し冗談も通じるようになってきて、少しずつ分かる部分が増えてきた。アルゼンチンババアと父と娘と、そこには人の表面だけ見て作り上げた自分のイメージで人の本来の部分、温かい部分であったり、人の傷ついた心の部分だったりが隠れてしまい、それを知っていく作業の中で人間らしくなっていく過程が描かれている。主人公が偏見で見ていた自分の考えが恥ずかしかった事にあとから気づく時、それはいつも偏見ばかりで何が真実か見えない自分を小説がよく客観的に見せてくれている。
物語は暖かく吹き抜ける風が通り過ぎるように終わる。あっという間に読み終える本。不思議な余韻を残して。
この記事をシェアする
サイト内投稿の検索
- トップ
- Staff Blog







 Top
Top About us
About us Plan
Plan News
News Photogenic
Photogenic Our story
Our story Staff blog
Staff blog Interior
Interior Coordinate
Coordinate Map
Map Education
Education CSR
CSR FAQ
FAQ