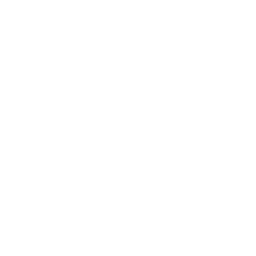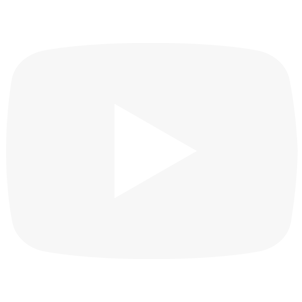Staff Blog
市川店
今を生きる。
投稿日:2019/5/31
1461 1
『いまを生きる』(原題: Dead Poets Society)は、1989年のアメリカ映画である。ロビン・ウィリアムズ主演、ピーター・ウィアー監督。第62回アカデミー賞で脚本賞を受賞した映画だ。
この作品には様々な場面で閉ざされた世界が演出されている。
例えばこの映画の主人公が通っている学校は全寮制となっており、その学校を卒業したら一流大学は約束されたのも同然の状態であることが映画の冒頭ですぐに分かる。
しかしそこに集められた若者たちのほとんどは、親の願いをかなえるためにその場所に来るという子供たちばかりである。親の言いつけをしっかり守ること以外はいつの日か自由になることを夢見る至って普通の若者たちであるが、この映画のキーマンであるロビン・ウィリアムズ演じる教師キーティングがその閉ざされた世界を開かれた世界へと変えていく。
そして若者たちはその開かれた世界の意味を知り、閉ざされた世界と開かれた世界の狭間で葛藤していく物語だ。
“今を生きる”そのように生きることができたなら、どんなに幸せだろうかと思う。
そのように自由に生きることもできない、大人たちが作り出した伝統や規律に縛られた環境でしか生きることができない、従順でいなければならない子たちがいて、夢を追うことは苦しくても、それがやりがいや生きがいになる。純粋に追うことができる人もいれば、親の期待を裏切ることができない、真面目な人もいる。正直、どちらが良いとか悪いとか、軽率に言えない気持ちになった。
私の今までの人生を振り返ってみると、親の願いを裏切ることができず、その道に進んだ時期もあれば、親の言うことばかり聞いていられなくなり、自分で思うがまま進んできた時期もあった。
しかし、親の願い通りに歩んでいた時期というのはもちろん自分が行きたくて行った道ではなかったが、なぜかその道が正しいとも思えてくるし、その道に行っていることで親に孝行ができているのではないかとさえ思えてくるのだ。
だが、親の願いとは逆に自分が進みたい方向に行こうとすると、親はとにかく反対してきた。あまりにも、反対されるとその進もうとしている方向が間違えているのではないかという錯覚に陥ったものだ。
なにかと大きな決断が必要なとき、自分という芯がしっかりもてていない私にとっては、このように親の言葉、周り人の言葉に左右されてきたのだ。錯覚に陥るということは自分の考えが明確ではなく、錯覚に陥ってしまうぐらいの考え決断でしかなかったのだと思う。
しかし、自らがつかみ取った可能性を理解してもらえず、自ら命を絶ったニールを私は完全に否定はできない。死んでしまった結果は取り返しのつかないことだが、ニールがその選択を取らなかったら逆にどのようになっていただろうか。
ニールは自分に嘘をついて生きていくようになるし、親の言いなりの人生を我慢し、諦めて生きていったのではないだろうか。
もしその中で、ニール自身に子供ができ、かつての自分のように、子供が自己に目覚め親に対して刃向かうような行動をとったら、ニール自身も父親にされたことを子供にもしてしまうのではないだろうかと思う。
また、ニールの父親もやはり、親に何事も強制され命じられてきたのではないかと思う。ニールは自ら命を絶ったことで悪循環を断ち切ってくれたと私は思った。
もちろん自殺は良いことではないが、この映画を通して、自分の考えに基準を作れと言われているように感じた。
先ほども述べたように、自分には基準というものがなく、親に言われるがまま、周りの意見に流されることが多くある。
ニールの行動を一つとってみても、勇気ある行動であると思ったし、自分自身を理解し、自分というものをしっかり持っているからこその行動であったと思う。自殺という部分だけをとってみると最悪の結果ではあるが、私は、ニールの勇気ある行動にカッコよくも思えた。
この記事をシェアする
サイト内投稿の検索
- トップ
- Staff Blog







 Top
Top About us
About us Plan
Plan Interior
Interior Photogenic
Photogenic News
News Our story
Our story Staff blog
Staff blog Coordinate
Coordinate Map
Map FAQ
FAQ